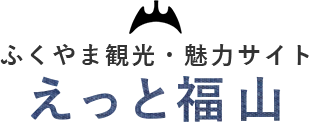本文
松永下駄(まつながげた)

製塩業が生んだ大衆の下駄
明治時代初期,松永では製塩業が盛んでした。塩を煮詰める薪を使って下駄を作ったのが松永下駄の始まりといわれています。
当時の主流は高価な桐材の下駄でしたが,松永下駄は「安価な大衆の下駄」として全国に広がり,機械化による大量生産で1955年(昭和30年)頃のピーク時には年間5,600万足の全国一の生産量を誇っていました。
「カランコロン」と鳴る二枚歯は松永下駄独自のものでしたが,最近では,右近ソフト(スポンジゴムが裏についたもの)が主流で,鼻緒の幅が広いものや備後絣で作られているものなどさまざまなバリエーションがあります。
今も昔も強いこだわりが下駄作りを支えています。