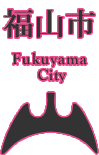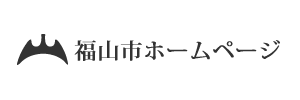戦火の記憶 石垣に残る炎の痕
1945(昭和20)年8月8日の夜、福山の町は空襲を受けました。市街地の約80%を焼失し、国宝に指定されていた福山城の天守と御湯殿は焼け落ち、城を支える石垣も被災しました。
福山城の石垣には主に花崗岩(かこうがん)が使われています。花崗岩は国内で多く産出し、加工しやすいため、昔から石材として広く使われていました。産地により色合いは異なりますが、国産のものは全体的に白っぽい灰色の石です。
空襲に使用された焼夷弾(しょういだん)は周囲一帯を燃やし、石垣は赤く変色しました。福山駅北口付近の石垣は表面が剝離し、角がとれて丸みを帯びており、高温の炎に長時間あぶられたことがうかがえます。
こうした空襲の傷跡を見ることができる花崗岩は市内随所にあります。被災した寺社では建造物の多くが焼失しましたが、石造りの鳥居や手水鉢は変色したまま今も残っています。寺町にある大念寺の石仏は焼夷弾を受けて顔の一部が破損しており、若松町にある水野勝成の五輪塔にも直撃した痕が残ります。
終戦から今年で80年が経ちます。福山城の天守と御湯殿は復元され、傷んだ石垣が残る福山駅の北口は公園として整備されました。福山城は江戸時代の城郭遺跡としてだけではなく、戦禍を語る戦争遺跡の一つとしても存在しています。
 福山駅北口広場の焼けた石垣
福山駅北口広場の焼けた石垣
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
文化振興課
084-928-1278