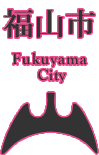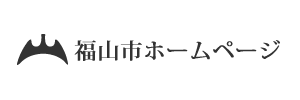江戸の面影 柳津の旧道
松永湾は江戸時代以降、塩田開発が活発に行われ、干拓と埋め立てによって土地を広げました。湾の東側に位置する柳津も平地はほぼ干拓地です。その山裾に沿うように旧道が通っています。この道は鞆・沼隈と松永を結ぶ交通の要衝であり、今も江戸から近代にかけての痕跡が随所に残っています。
神村へ向かう山道と旧道との分かれ道には、天辺に擂鉢を被せられた四ツ堂があります。その中には、台座に「元治二丑(1865)年」と刻まれた地蔵菩薩が安置されています。また付近には、自然石を割って造られた素朴な常夜燈も残されており、1776(安永5)年に塩田が造られるまですぐ海に面していました。
潮崎神社から北へ少し歩いたところには、穏やかなお顔のお地蔵様がいます。台座の正面に「供養導師山南悟眞寺七世 願誉上人(くよう どうし さんな ごしんじ ななせい がんよしょうにん)」、右側に「正徳元辛卯天(しょうとくがん かのとう てん) 七月廿四日」と刻まれています。悟真寺は旧道を鞆方面に7キロメートル程進んだ沼隈町にあるお寺です。創建は古く、江戸時代に入ると藩主の松平家や阿部家に庇護されました。右側に刻まれた正徳元年は1711年で、お寺の由緒によると、この頃の住職に願誉上人の名があります。これもまた旧道を通じた当時の交流を物語る痕跡のひとつです。
戦後、塩田は廃止され、かつての湾の風景を見ることはできなくなりました。それでも車の往来が多い道を少し外れた旧道沿いを歩けばかつての建造物や石造物を見ることができます。



手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
文化振興課
084-928-1278