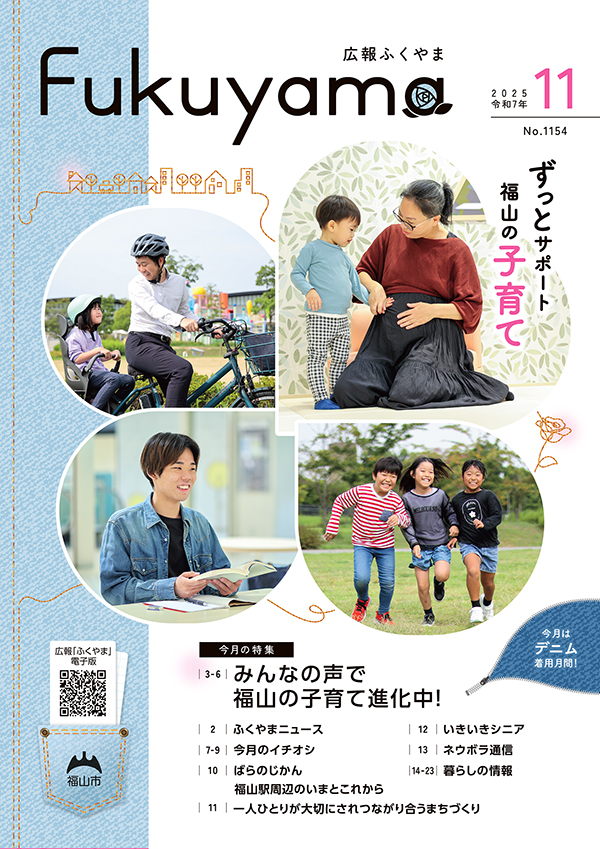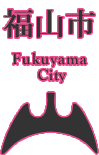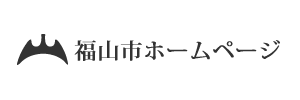干拓地を支える水路 多治米沖川(おきがわ)の灌漑(かんがい)対策工事記念碑
11月15日に本市は近代水道通水100周年を迎えます。水を安定的に確保するため、古くから粉骨砕身の闘いが繰り広げられてきました。
多治米小学校南側付近から川口交流館方面へ、西から東に多治米を横断する「沖川」という水路があります。これは江戸時代に福山藩の干拓事業で多治米村が造成された際に整備されたものです。
遠浅の海を干上がらせて形成された干拓地で最も課題となるのが、真水の確保です。湧き上がる水には塩分が含まれています。沖川は芦田川の水を多治米村内へ取り込む唯一の水路で、この水こそが住民の生活と農業の生命線となっていました。雨量の少ない時は川の上流へ浚渫(しゅんせつ)に出掛けたり、近隣の村々と話し合って時間制で取水したりするなど、多大な苦労の先に水を手に入れていました。
明治時代には「新川(しんかわ)」と呼ばれる水路が新たに整備され水利は向上しましたが、沖川は土砂の堆積により徐々に水深が浅くなり、水量が減少していきました。
このような状況の中さらに1939年に大干ばつが発生し、貯水機能をもつ水路の築造が急務となりました。住民たちは改修工事を願い出て、翌年には沖川の幅が5.5メートルから9.9メートルに拡げられ、貯水量11万3000立方メートルの水路が完成しました。
灌漑対策工事記念碑にはこの改修工事の経緯が記されています。住民たちの努力と奮闘により、水を安定的に確保できる水路が完成した喜びが込められているのです。
※浚渫…堆積した土砂などを取り除き、水底を掘り下げること


手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
文化振興課
084-928-1278