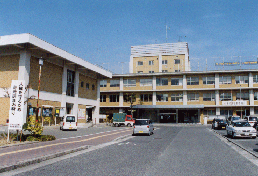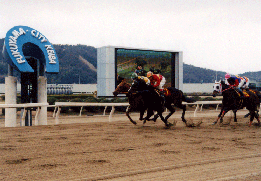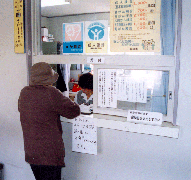本文
ふくやま市議会だより第5号 平成15年第1回市議会定例会
印刷用ページを表示する 掲載日:2003年5月1日更新
平成15年3月 定例市議会 平成15年第1回市議会定例会は、2月28日から3月25日までの会期26日間で開催されました。
総額1,349億6,800万円の新年度一般会計予算など68議案のうち修正可決1件を除き、いずれも原案どおり可決しました。
また、議員提出の市議会委員会条例の一部改正や農業委員の議会推薦ならびに意見書2件をいずれも原案どおり可決しました。
3月定例会では、7人の議員が会派を代表して質問を行いました。その概要は次のとおりです。 |
質問および答弁(要旨) 質問項目
近隣市・町との合併(新政クラブ) | 質問 15年2月3日、内海町・新市町の合併により新たな飛躍を目指した中核市福山がスタートした。県の合併パターンでは、府中市・神辺町・沼隈町も含まれているが、今後の対応は。 | | | 答弁 府中市では、当面は上下町との合併が目標になっており、本市との合併はその後の段階になるものと受け止めている。
沼隈町とは、15年1月31日に村上町長から事務協議を開始したいとの申し出があり、新年度から事務調査を実施し、具体の取り組みを行う考えである。
また、神辺町では町長から、15年度中にアンケート調査を実施し、その結果を見て判断したいとの考えを聞いている。
いずれにしても、合併協議の具体の申し入れがあれば、受け止めていく考えだが、合併するのであれば合併特例法の期限内に実現すべきものと考えている。 |
| ◇関連した他会派の質問 ・市民連合(沼隈町との進捗と今後の対応) ・公明党(沼隈町・神辺町との見通しとスケジュール) |
今後の市民センター構想(市民連合) 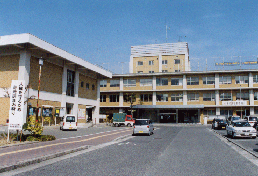 | 松永支所全景 |
| 質問 地方分権が進み、市も「庁内分権」を提唱し、「市域内分権」が必要な今、これまで「年度内には方向性を」と答弁された南部・西部市民センター設置は、市民からの強い要望でもある。今後の考え方は。 | | | | 答弁 より充実した市民サービスの提供と地域活性化の拠点施設として、これまで北部・東部市民センターを整備してきた。13年度新たなセンターの建設について調査・検討をしてきた結果、合併要因等も考慮しながら次は西部地域への建設に向けて取り組みたいと考えているが、今後の財政状況等も含めて建設年次は慎重に検討していく。 |
住民の意見の取り上げ方(明政会) | 質問 首長や議員の選挙で全権を託したのではなく、重要事項は住民自らの手で決定したいという思いから、住民投票条例案を提案している自治体もあるが、それら一連の流れへの見解は。 | | | 答弁 政策形成過程への市民参加をはじめ市民の合意を形成していくことは、円滑な行政運営に不可欠なものであると考えており、男女共同参画基本計画の中間まとめに対する意見募集など、これまでも取り組みを行ってきた。
住民投票については、議会制民主主義とのかかわりなどからさまざまな議論があり、今後の動向などを見極めていく必要があると考えている。 |
選挙区の区割り(明政会) | 質問 合併後、面積も430.28k平方メートルと全国でも41番目の広さになり、風土・気候も大きく異なる地域の住民の福祉と健康を守るためにも、市全体のまちづくりを考える一方、各地の現状を踏まえた議論をする必要もあり、今後、選挙区の区割りも考える必要があるのでは。 | | | | 答弁 市町村の議会の議員の選挙は、指定都市を除き原則として選挙区を設けないこととし、町村合併等により地域が広大であるなど市町村の実情に応じて特に必要がある時は条例を制定することとなる。このことは、議員に係わりのある課題であり、十分に意見等聴きながら研究していく。 |
同和行政(日本共産党) | 質問 同和地区実態調査費が計上されており、調査結果が同和行政継続の根拠にされる危惧があるが、撤回は。解放会館を人権交流センターとする提案は、「人権」の名での同和行政継続であり、部落解放同盟の事務所の撤去、団体補助金の廃止で同和行政終結は。 | | | 答弁 新年度に予定の「同和地区実態調査」「市民意識調査」は、18年度以降の人権行政の方策を検討する基礎的資料とすること等を目的として実施するものであり、内容等は調査の実効が上がるよう検討していく。
解放会館における自主的運動団体への使用許可は、さまざまな人権課題の解決を目指す(仮称)福山市人権交流センターの設置目的を踏まえ対応していく。
自主的運動団体への補助金は、「市答申」「基本方針」を踏まえ所要の整理を行っており、施策の進捗状況や活動実態等を勘案しながら、助成のあり方を検討していく。 |
| ◇関連した他会派の質問 ・水曜会市民クラブ連合(市同和行政基本方針に基づく取り組みほか) ・市民連合(解放会館・集会所のあるべき姿と今なお残された課題に
ついて今後の取り組み) |
(仮称)シルバーサロン設置(新政クラブ)  | ←手芸の会(向丘ふれあいプラザ) | 
| ←高齢者ダンス教室(新市) |
| 質問 新年度施策の中で小学校区に(仮称)シルバーサロンの設置が示されている。公的遊休施設を利活用しての施設整備は、長年要望してきた事であり、公的施設には小・中学校も含まれるものと理解しているが、見解は。 | | | | 答弁 ふれあいプラザの立地していない小学校区を対象に既存の公共施設を高齢者の憩いの場として整備しようとするものだが、学校教育においては、今後ますます学習指導方法が多様となり教育施設としての必要性がさらに高まる事が予想され、それに対応できるスペースの確保を見極めるなかで施設の利用可能な学校は対象施設として取り組む考えである。 |
| ◇関連した他会派の質問 ・水曜会市民クラブ連合(事業の内容) ・市民連合(今後の方針と遊休公共施設のない地域での取り組み) |
行財政改革(水曜会市民クラブ連合) | 質問 国では現在、退職金の見直しを検討している。本市は、2007年度からの10年間定年による大量退職者のため、基金積み立てを行っているが、退職金の見直しも必要ではないか。 | | | | 答弁 国では、退職手当の支給水準等の見直しが現在論議されており、また、能力・実績等が十分反映された給与制度の構築や公務員制度改革についても検討が進められている。本市でも、「福山市行財政改革大綱」に基づき、国の状況を見極め、適切に対応していきたい。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・新政クラブ(民間委託・民間活力の導入) ・誠友会(市民生活に即応した改革の実現、退職金の支払いと財政運営ほか) ・明政会(各種審議会等の運営と人選、職員研修の内容) |
新年度予算編成(水曜会市民クラブ連合) | 質問 合併初年度にあたり、また今年で12年目の、ある意味では節目の予算編成に対する市長の率直な思いと配慮された点は。合併建設計画を組み入れた財政見通しと市債残高に対する返済計画は。 | | | 答弁 景気動向や国の制度改正などから、固定資産税が大幅に減少し、地方交付税なども減少が見込まれ、扶助費や公債費等が高水準で推移するなか、退職手当の増加など財政状況は大変厳しく困難な予算編成であった。
新年度は合併初年度の当初予算であり、本市の将来を見据えた施策の展開を図るため新行財政改革大綱の下、経常経費などの抑制に向け全庁に見直しを指示し、国の補正予算を活用した3月補正予算での対応も視野に施策の選択と重点化を図ることとし、予算編成を行った。 |
| ◇関連した他会派の質問 ・新政クラブ(今後の財政見通し) ・誠友会(合併をめぐる予算編成) ・市民連合(自主財源の確保) |
合併に伴う財政問題(公明党) | 質問 合併に伴う財政問題について、新年度予算案は、合併2町を含む3団体合計分と比較すると1.3%増に留まり、更に合併増額分を考慮すると前年度比マイナスが推定される。自主財源確保に向け一層の対策が求められるが、市長の考えは。 | | | 答弁 自主財源確保について、市税を中心とした収納率向上は最重要課題として取り組んでいる。
今後とも、納期内自主納付に向け市民啓発を実施するとともに、早期に滞納処分に着手するなど法令に基づく厳正な対処を通じて、自主財源の確保を図っていく。 |
市営競馬場外発売所(誠友会) ふくやま市営競馬場 | 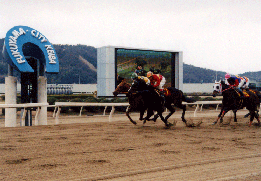 |
| 質問 競馬事業は、厳しい環境にあるが、収支見込みが2年連続黒字となり、関係者の取り組みを評価する。今後売上低下に歯止めをかけるため、地域住民の理解を得るなか、民間活力による場外発売所の拡充に向けた推進状況は。 | | | | 答弁 場外発売所の設置は、現在まで3ヵ所を推進決定している。南松永町と神辺町の計画は、地元町内会の理解が得られるよう提供者で精力的に取り組まれており、地域との十分な調整がなされるなかで推進を図っていきたい。島根県三刀屋町の計画は、町長の同意を得たので今後、警察協議や農林水産大臣への承認申請などの手続きを進めていく。全国的に例のない取り組みでもあり、適時適切に事務処理が求められており、今後設置申請の動向を踏まえて検討していく。 | |
景気・雇用問題(公明党)  | ハローワーク相談窓口 |
| 質問 雇用・中小企業セーフティネットの円滑な制度運用に向けて、関係諸機関との連携強化と一層の市民周知が必要。「離職者支援資金貸付制度」並びに「資金繰り円滑化借換保証制度」、「勤労者生活安定資金」および「景気対策特別資金」の利用状況と課題は。 | | | 答弁 離職者支援資金は2月末で9件、融資総額1,480万円で、県民だよりやラジオ等で周知されており、制度の利用促進を図るため連帯保証人の要件緩和や償還期間の延長が図られた。
資金繰り円滑化借換保証は2月末で102件、保証総額13億9,156万円で、中小企業庁のホームページや新聞等で周知されている。
勤労者生活安定資金は1月末で24件、融資総額2,712万円、また、景気対策特別資金は1月末で305件、融資総額20億3,560万円となっており、これらは広報ふくやまや関係団体の広報紙等、取扱金融機関等の窓口へのパンフレット展示などで周知を図っている。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・市民連合(雇用対策としての公共事業の創出、ワークシェアリングほか) |
入札制度とチェック体制(水曜会市民クラブ連合) | 質問 市内の公共工事入札を巡り暴力団の介入や談合に対して、市民の不平や不安が募っている。14年の12月定例市議会で「暴力追放都市宣言」の一層の推進を決議したところだが、行政サイドとして制度やチェック体制等の問題があるが取り組み状況は。 | | | | 答弁 14年10月、市から福山地区建設協会へ建設工事の適切な推進等について、文書で申し入れをし、7項目の決議をした旨の報告を受けている。再発防止に向け、福山市建設工事暴力団対策措置要綱の厳正な運用を始め、新たに福山地区入札問題等連絡会議や広島・岡山暴力追放連絡会議を立ち上げており、行政間にとどまらず、警察当局を含め情報交換を緊密にし暴力団の介入や不正行為の防止に努めていく。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・新政クラブ(受注希望型入札制度、資材の標準単価、VE方式) ・誠友会(入札・契約制度の改善、入札監視委員会) ・市民連合(入札・契約制度の改善策) ・公明党(受注希望型入札制度、入札監視委員会) ・日本共産党(暴力団介入などの実態調査を求めた要望書の実行ほか) ・明政会(工事施工の管理体制、低価格入札者の落札基準ほか) |
走島地区の諸課題(水曜会市民クラブ連合) | 走島診療所 |
|---|
 | 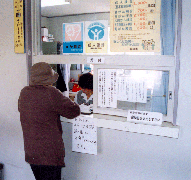 |
| 質問 昭和47年診療所が設置されたが、簡易な診察や治療しか出来ない状態となっている。 また、現在週3回のみの診察で、それ以外は無医村地区の状態となり、改善が待たれるが、考えは。 | | | 答弁 現在は走島診療所運営委員会が民間病院と連携を図りながら運営している。住民が安心し、必要な医療の確保ができるよう運営委員会をはじめ関係機関と協議するなかで体制の整備を検討していく。
また、急病人の発生等緊急時は、通報により水上消防署の救助艇で搬送に努めており、消防ヘリコプターも小学校のグラウンドを緊急離着陸場として活用するなど、関係機関との協力・連携を図りながら安心かつ迅速な搬送に努めていく。 | |
障害者支援費制度への移行(市民連合) | 質問 これまでの「措置制度」から15年4月「支援費制度」に移行するが、スムーズな制度移行へ危惧の声もある。実態把握の現状と制度移行への進捗状況は。また、十分なサービス提供体制は確保できるのか。 | | | 答弁 申請に基づき14年11月から訪問調査を実施し、既に98%の実態を把握している。今後支給決定を行い、受給者証の交付とサービス提供事業所の情報提供を行っていく。
サービス提供体制について、支援費制度では、利用者がサービスを選択できるための提供体制の整備が重要であり、事業者の参入促進に努めている。短期入所事業では、サービス提供体制が要望に比べて不足が予測されている。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・水曜会市民クラブ連合(移行への準備段階での課題) ・新政クラブ(移行への説明と手続きの状況) ・公明党(導入に向けた課題と対策) ・日本共産党(職員体制・審査体制の確立など公的責任) ・明政会(サービスへのニーズと居宅介護事業者の状況ほか) |
男女共同参画センター(市民連合) | 質問 センターの持つ役割は、学習・情報・相談・交流など基本機能の充実はもちろん、シェルターの整備、また、いわゆるセクハラやDV等の発生後のフォローなども必要かつ重要。機能の更なる拡充が必要では。 | | | 答弁 学習・情報・相談・交流機能を基本に、地域に男女共同参画を根付かせるための学習や研修事業により、核となる人材を育成していきたい。
センターでの相談が市民に分かりやすく利用しやすい総合相談窓口となるよう努め、セクハラやDVなどさまざまな悩みを持つ女性に対して、解決策を一緒になって探していくと同時に、自ら生きる力を取り戻していくような心理的回復と自立を支援する方向を目指す。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・新政クラブ(センターの運営) ・公明党(既存2施設の利活用、センターの相談機能・情報機能) ・明政会(今後の運営の具体と指針) |
少子化対策(公明党)  | 延長保育(多治米保育所) |
| 質問 ふくやま子育て応援センターは、休日保育の実施や相談機能もあるが、利活用の実態と子育て世代が抱える課題は。保育所の待機児童ゼロ、乳幼児医療助成の就学前までの拡充など本市の先進的な取組みを踏まえ、今後の少子化対策の中長期展望は。 | | | 答弁 子育て応援センターの利用状況は2月末で相談件数1,586件、情報提供1,756件で13年度に比べ情報提供が大幅に増加しており、休日保育は延べ1,605人、1日平均26人の利用となっている。
相談内容は、保護者自身の育児不安に関するものが多く、子育て支援の取り組みを一層充実していく必要があると考えている。市民への周知は、ホームページをはじめ全市的に保育所で行われている子育て支援事業や関係機関へのチラシ配布などでPRに努めている。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・市民連合(保育施策の今後の拡充策) ・日本共産党(保育料の引き下げ、保育士の配置の充実) |
放課後児童クラブ(日本共産党) | 質問 これまでも充実発展に努力をされているが、更に全学区での開設、利用料の軽減、利用を希望する児童の学年延長、とりわけ障害児は6年生まで対象拡大、多人数クラブは複数の教室整備等施策の充実は。 | | | 答弁 今後の開設では、残る学区は少人数であり、開設方法や運営方法等について総合的に検討していきたい。利用料は受益を受ける市民負担の公平性の確保から応分の負担とし、経済的な事情その他特別の理由により減免をしている。
利用対象学年は、現行どおり小学校3年生までと考えており、障害児の利用は14年度5年生までを受け入れてきたところで、15年度から6年生を受け入れることとしている。
施設・設備の改善は、緊急度、必要度の高いところから対応しており、計画的な維持、改修に努めていく。 | |
| ◇関連した他会派の質問 ・市民連合(事業の全学区開設への方針) |
(仮称)市民の館整備(誠友会)  | 市民会館跡地 |
| 質問 民間資金を活用したPFI手法を導入し、図書館を核とした複合施設建設を計画されているが、PFI導入可能性調査による縮減効果が7%の根拠や公共サービスの提供、民間企業の保障やリスク責任などの問題については。 | | | 答弁 財政負担の縮減効果の試算では、図書館の形態の変化や、20年を経過すると施設の大規模改修が必要となるが、改修経費が現時点では予見できないので、事業期間を20年間とした。
サービス水準は、民間事業者の一体的な運営・維持管理により、経験やノウハウを活かした業務の効率化と施設利用者の利便性の向上が図れると考える。
事業実施に当たっては、発生する事故等の損失で想定できるリスクを洗い出し、負担すべき者を明確にした上で、詳細な事業契約を締結し、公共がサービスの内容を常に確認し、業務の実施報告書等の提出を義務付け、事業期間を通して適正な履行を確保することとなる。 | |
|