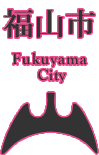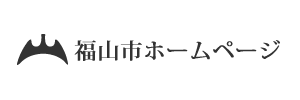主要産物から伝統的工芸品へ 備後絣(がすり)
久留米絣や伊予絣とともに日本三大絣といわれる備後絣は、江戸末期、芦田町出身の富田久三郎が井桁文様の絣を販売したことに始まりますが、福山は元々織物が盛んな地域でした。
日本の絣の技法は綿織物の普及とともに発展したため、歴史はそう古くありません。原材料である綿の栽培が本格化したのは江戸時代に入る少し前で、それまでは輸入に頼る高級品でした。
福山藩は新田開発に力を入れたため、綿の栽培を奨励しました。干拓された土地は塩分を含んでおり、すぐに稲作を行うことができません。一方、綿は塩に強い作物で、土中の塩分を吸収し養分を蓄えます。商品価値も高く、繰綿(くりわた)や織物に加工されて付加価値がつきます。土壌改良に有効でなおかつ高値で取引される綿が、藩の重要な作物になるのは必然でした。
時代が下ると藩内のほとんどの村で農家の女性が木綿織に従事するようになります。肌触りがよく丈夫な綿織物は江戸半ばには普及し、染料である藍の栽培とともに、色柄のある織物が織られるようになりました。
絣は織る前に糸を染め、染め残した部分を組み合わせて文様を作ります。染色の工程も多く、細かい文様になるほど高度な技術を必要とします。備後絣は経糸(たていと)だけを染め残した経絣(たてがすり)から始まり、次第に井桁や市松等の幾何学模様に進化しました。家ごとに引き継がれた見本帳には様々な文様の小さな布が貼り付けられ、織り手の情熱を感じます。


※しんいち歴史民俗博物館では備後絣の保存と活用に取り組んでいます
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
文化振興課
084-928-1278