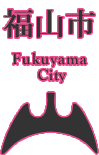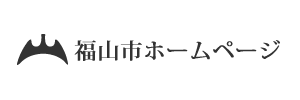個性いろいろ 埴輪の形
ゆるくデフォルメされた人物やかわいらしい動物の形をした埴輪を、今はさまざまな場所やメディアで見ることができます。
埴輪は古墳の周囲や頂部に置かれる土製品です。本市には900以上の古墳がありますが、埴輪の出土はそう多くありません。
比較的多く出土するのは、穴の空いた土管を短く切って立てたような円筒埴輪です。古墳の周囲に並べ、古墳の聖域を区切る役割を持っています。市史跡イコーカ山古墳は現在この区切りが分からなくなっていますが、1962年の記録では古墳の周りに円筒埴輪が二重に巡らされていたとあります。県史跡松本古墳では、築造された当初の位置で円筒埴輪の底の部分が発見されたことが、古墳の形状を特定する根拠の一つとなりました。
動物などを模した形象埴輪は松本古墳や池の内2号古墳、千田平ノ前古墳等から出土しています。中でも千田平ノ前古墳からは、馬、家、盾、入れ墨をした人物の頭部といった様々な形の埴輪が出土しました。墳丘は完全に失われていましたが直径約10メートルの円墳で、小さな古墳でもたくさんの埴輪が使われた6世紀前半の古墳と考えられています。
作られてから1500年以上経過した埴輪は、風雨にさらされて傷み、倒れて壊れ、完全な形で出土することはほとんどありません。土中の水分により柔らかくなった破片を周囲の重い土ごと削って取り上げることもあります。その後、洗浄・修復・図面実測など、多くの工程を経て埴輪は展示され、今の人々を楽しませてくれます。
 千田平ノ前古墳 埴輪(右から馬、家、盾、人物)
千田平ノ前古墳 埴輪(右から馬、家、盾、人物)
 千田平ノ前古墳 盾形埴輪出土状況
千田平ノ前古墳 盾形埴輪出土状況
※しんいち歴史民俗博物館と神辺歴史民俗資料館では市内で出土した埋蔵文化財を展示しています。
(記事内で紹介した埴輪は常設展示されておりません)
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
文化振興課
084-928-1278