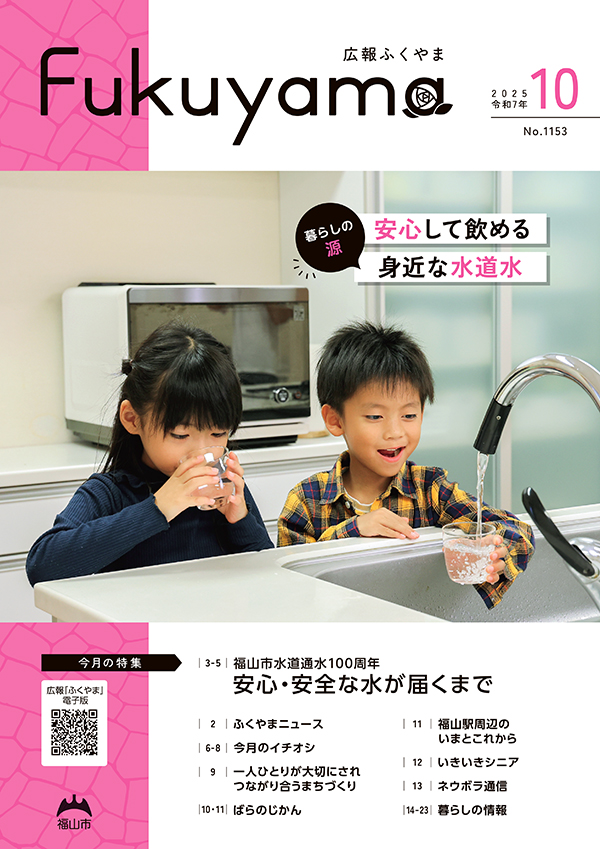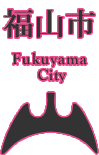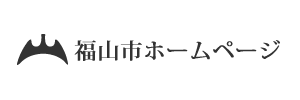尾道石工の技術を伝える 狛犬の親子
神辺町の下御領八幡神社は天平年間(729年から749年)の創立と伝えられ、大分県の宇佐八幡宮より勧請し、備後国分寺の鎮守社であったといわれています。この神社の境内には、狛犬の親子がいます。
一般的に狛犬には神社を守護する役割があり、向かって右側に口を開いた「阿形(あぎょう)」、左側に口を閉じた「吽形(うんぎょう)」の二体が一対で置かれています。しかし下御領八幡神社の狛犬は四体が二対となり、玉の上に両前足をかけて鎮座しています。そのうちの本殿に向かって左奥の狛犬は、他の三体と異なり大小二体の親子が一つの台座に乗る「子取り狛犬」です。親である吽形の狛犬の足元で、こどもが玉にしがみつきながら左足を台座にかけています。玉に登ろうとする姿とも、滑り落ちそうになっている姿とも見える愛らしい様子です。
この子取り狛犬は、台座の刻銘によると、1903(明治36)年9月に尾道の石工である中谷清兵衛によって制作されました。
尾道は古くから港町として栄え、また石材が豊富であったためそれを石造物に加工する職人が集住していました。尾道石工の銘が見える最も古い作例は、愛媛県松山市道後公園内にある湯釡で1531(享禄4)年の刻銘が残っています。こうした石造物は江戸時代には尾道を代表する特産品として、北前船で各地に運ばれました。その中でも特に優れた彫刻技術が必要となる狛犬は、高級品として広まりました。
本市にも尾道石工による石造物が数多く残っています。下御領八幡神社の遊び心のある狛犬も、こうした技術を今に伝えてくれるものです。

手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
文化振興課
084-928-1278