本文
福山市水道の歴史(2) 「福山市誕生と近代水道」
福山市水道の歴史(2) 「福山市誕生と近代水道」
水道の必要性
明治時代に入ると、旧水道にいくつかの問題が立ちはだかります。
- 旧水道の老朽化
⇒ 各所で汚水が流入したり、伝染病が頻繁に発生 - 人口増加:約2万人(明治時代)
⇒ 清浄な「水」を得ることが困難 - 地方新興都市の発展
⇒ 大量の清浄な「水」が必要
旧水道に立ちはだかる問題を解決するために、清浄な水を大量に供給できる、「近代水道」の布設が求められました。
⇒ 川の水をきれいにし、消毒してから送る現在の「水道」の建設に向けた動きが加速していきます。
町制時代
1889年(明治22年)に「福山町」が誕生して以降、旧水道を水源に、一大改修を行う議案を町議会に提出したことを皮切りに、井戸試掘などの水源調査を開始しました。
| 1896年(明治29年) | ろ過による良水と旧水道を水源に、一大改修をはかる議案を町議会に提出 |
| 1898年(明治31年)~ | 井戸試掘など、水源調査を開始 ⇒ 水源問題で行き詰まり、断念 |
| 1908年(明治41年)~ | 臨時調査委員による研究・企画(旧水道を廃止して改良上水道布設) |
| 1909年(明治42年)~ | 東京から工学博士などを招き、実地調査、ボーリング調査 |
| 1910年(明治43年) | 水道布設の具体案を町議会に提出(芦田川より引水)⇒ 議決、国庫補助申請 |
水道布設に向け、国庫補助申請を行いましたが、「水道新設の補助は、町以下においては、一切補助しない」という国の内規によって、またも、水道布設は頓挫することとなりました。
⇒ 「阿武信一(あんのしんいち)」町長が就任すると、近代水道建設の財源として国庫補助を受けるべく、市制施行をめざし、奔走することになります。(1915年(大正4年)12月、町議会に市制施行案を上程)
市制施行
1916年(大正5年)7月1日、念願であった「福山市」が誕生し、初代福山市長には「阿武信一(あんのしんいち)」町長が選任されました。
| 【市制施行日の新聞記事】 | 【市制記念はがき】 |
|---|---|
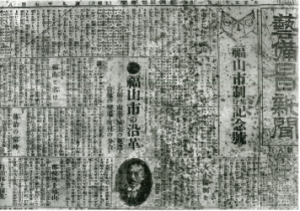 |
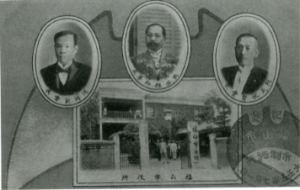 |
市制施行により、水道布設に必要な国庫補助を受ける必要条件が整いました。
⇒ 「市」として、水道建設に着手していくこととなり、まずは「水源」の場所を決断する必要がありました。
【水源問題】
- 水源を地下水に求めるか?
- 水源を地表水(芦田川)に求めるか?
⇒ 両者を比較検討し水源を決断するため、9名を選任し調査に着手します。
しかし、水源問題は進展せず、国に技師の派遣を要請することとなり、福山近辺の綿密な地下水調査の結果、福山には、かなりの量の地下水があることが予測されるものでした。
近代水道の建設って一筋縄ではいかなかったんだね!







