本文
はきもの玩具館 はきもの 第1展示室

「労働とはきもの」「信仰と行事のはきもの」「芸能と遊びのはきもの」
「雪のはきもの」「貴族と武将たち」「皮沓(かわぐつ)と足袋」など、
生活の中での様々な場面のはきものを展示しています。
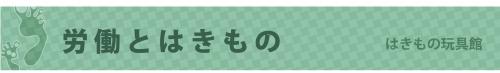
人は、この地上に暮らし始めた頃、毎日の食べ物を求めて、険しい山や寒い雪の中、いばらの草原や岩だらけの急流などを移動していました。
自分の身体を保護する衣服やはきものは、狩猟の時代から作り出され、農耕の時代には様々な工夫が見られました。

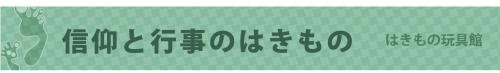
毎日の厳しい労働の合間には、ときには仕事を離れて集い会うさまざまな行事がありました。
村の結婚式や葬式、季節を彩る行事は、素朴ながらも人々の心を結びつける大切なものです。
また、神社や寺に、はきものを納める(奉納)風習が全国各地に見られます。
これは、神や仏に収穫を感謝し新しい年の豊作を願うものです。
さらに、悪霊や悪い鬼を追い払うためや、足が丈夫になるよう願うものなど、庶民の信仰とはきものとの関係は広くて深いつながりがあったのです。

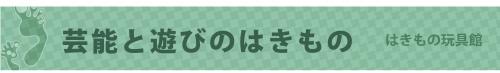
舞台で演じる伝統芸能である歌舞伎や人形浄瑠璃、楽しい娯楽であったサーカスなどにも工夫したはきものがありました。
竹馬や缶下駄など遊びの中のはきものの中にもたくさんの工夫がありました。

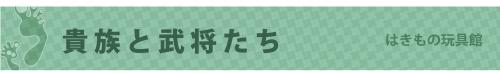
殿上人(デンジョウビト)といわれた貴族たち、また、鎌倉時代から幕府を開いた武士は、一般の庶民とは異なる生活のスタイルがあり、衣服やはきものにおいても独自のものがありました。
また、大昔の古墳からは死者へ履かせた金属性の靴も発掘されています。


屋根の雪降ろしや雪踏み、炭焼きなど、雪のはきものは雪国の生活に欠かせません。
藁沓(ワラグツ)という雪国独自の履物や、雪の中を歩く時足がうもれないようにする「かんじき」という道具も生まれました。


広げた皮の上に足をのせ、周りの皮を持ち上げて足を包み込み、ふちに穴をあけてヒモをとおして締め付ける、いちばん簡単なはきものの作り方です。
踵が無くて底がやわらかく足にピタッと合う、くつというよりも足袋に近いはきものです。








