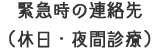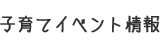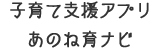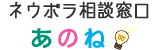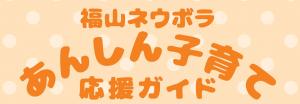本文
児童手当制度の概要について
物価高対応子育て応援手当については、次のリンク先をご確認ください。 ⇒物価高対応子育て応援手当について
福山市に転入された方、出生等で児童を養育することになった方は、申請が必要です
出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。申請が遅れた場合は、さかのぼって支給できません。
子ども医療費助成事業は申請期限が異なりますので、次のリンク先をご確認ください。
⇒子ども医療費受給資格申請の期限について
対象者
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人 (公務員の人は勤務先で申請してください。)
※請求者(生計中心者)も、児童も、国内に居住していること(留学の場合を除く)。
※児童が児童福祉施設等へ入所している場合、児童自立生活援助を受けている場合や里親に委託されている場合は、施設等・里親へ支給します。
手当月額
|
0歳~3歳未満 |
(第1子・第2子) 15,000円 |
所得制限はありません | |
|
(第3子以降) 30,000円 |
|||
|
3歳~高校生年代 |
(第1子・第2子) 10,000円 |
||
|
(第3子以降) 30,000円 |
|||
※児童の人数は22歳到達後最初の3月31日までの間にある子を数えます。
支払日
偶数月の各月15日(金融機関が休みの時はその前日)に支給月の前月分までの2か月分をまとめて振込みます。
※振込通知は行っておりませんので、通帳を記帳してご確認ください。
| 支給(予定)日 | 支給月分 |
| 10月15日 | 8月~9月分 |
| 12月15日 | 10月~11月分 |
| 2月15日 | 12月~1月分 |
| 4月15日 | 2月~3月分 |
| 6月15日 | 4月~5月分 |
| 8月15日 | 6月~7月分 |
出生 、 転入等により認定になった人はその認定開始月分からの支給となります。
金融機関が休業日の場合は、その前営業日に支払います。
認定請求の方法
出生・転入等の場合は申請が必要です。
支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。
児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし、支給要件に該当した日が月末に近い場合は、支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。
<申請に必要なもの>
・預金通帳(請求者名義のもの)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
・委任状(請求者・配偶者以外の方が代理で申請する場合)
※申請の際に追加の書類が必要となる場合があります。
各種届出
次の事由に該当する場合は届出が必要です。
(事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。)
◇ 受給者が市外へ転出したとき
福山市での受給資格は消滅します。転出先の市区町村で新たに「認定請求書」を提出してください。
◇ 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
受給者が公務員になったときは、各勤務先からの支給となります。すみやかに福山市へ「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員でなくなったときは、勤務先での受給資格が消滅しますので、福山市(または住所地の市区町村)へ「認定請求書」を提出してください。
◇児童が増えたとき
出生などにより支給対象の児童が増えたときには「額改定請求書」を提出してください。
◇児童が児童福祉施設等に入退所したときなど
児童が施設等へ入退所したとき、児童自立生活援助を受けたまたは終了したとき、里親に委託されたまたは委託解除されたときは、「認定請求書」、「額改定請求書」、「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
◇ 児童と別居するようになったとき(受給者・児童の住所変更)
児童と別居するようになったときは「住所変更届」を提出してください。 別居により児童を養育しなくなったときは 、 「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
◇ その他の届出
・受給者または対象児童が国外に居住するようになったとき
・振込先口座を変更するとき(受給者名義のみ)
・公金受取口座の利用を希望するときまたはやめるとき
・受給者または対象児童が死亡したとき
・対象児童を監護養育しなくなったとき
・受給者が刑事施設等に入所または勾留されたとき
・配偶者について、住所、婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき
・離婚協議中であり同居している父母として認定されていた者で、その後離婚が成立したとき
・3歳未満児童を養育している受給者について、受給者の加入する年金が変わったとき
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、学費や生活費等の負担がなくなったとき
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、名前や住所等に変更があったとき
・受給者が公務員になったとき など
◇現況届
現況届は、毎年6月1日現在の状況を確認し、引き続き児童手当の支給要件に該当しているかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人
- 児童と別居をして監護している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が算定対象になっている人 など
※現況確認の結果の反映は10月支給分(8・9月分)から行います。
8月支給分(6・7月分)は、前年度の所得を踏まえた受給資格に基づく支給となります。
※生計中心者が変更になった場合、受給者からの届出により、受給者変更も可能です。
寄附制度について
児童手当制度では、寄附制度を設けています。寄附金は児童・子育て支援事業のために利用されます。関心のある方はお問合せください。
公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
公金受取口座として登録する口座はマイナポータル上でいつでも変更することができます。
次の場合は、届出が必要ですのでご注意ください。
〇届出が必要な場合
・公金受取口座を希望する場合
・公金受取口座の利用をやめる場合または抹消した場合
※マイナポータルで公金受取口座を変更した場合は、金融機関変更届の届出は不要です。
※公金受取口座の登録・変更を行う際は、手当支給月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)の前月中に手続が必要です。
申請先
ネウボラ推進課 (市役所7階)
松永、北部、東部、神辺 保健福祉課
内海、沼隈、新市、鞆、芦田、加茂 支所 保健福祉担当
水呑分室、熊野分室、山野分所