本文
食中毒予防の3原則
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

食中毒の大部分は細菌によるものです。食中毒を予防するためには、次のことを守ることが大切です。
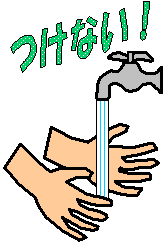 |
  (洗う・分ける・包む) 食中毒菌が手や調理器具を介して食品に付着し、増えることで食中毒を起こすことがあります。 基本は手洗いです。自らが細菌の運び屋にならないように、こまめに手を洗いましょう。 調理器具もしっかり洗いましょう。 包丁・まな板は、肉用・魚用・野菜用に分けて使いましょう。 肉や魚などを保存する時は、他の食品に肉汁がかからないように、袋や容器に小分けしましょう。 |
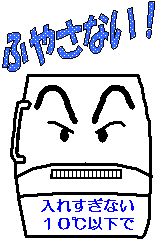 |
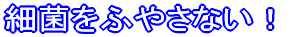  (冷凍・冷蔵・室温で長く放置しない) 一般に食中毒菌は、室温状態(10℃~40℃)の時、急速に増殖します。(腸炎ビブリオは8~10分で2倍に増えます!) 冷蔵庫で保存しなければならない食品を買った場合は、寄り道せず、帰ったらすぐ冷蔵庫に入れましょう。 また、冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。 冷凍食品の解凍を室温でおこなうことは禁物です。中心部が解凍されるまでの時間に表面温度は室温と同じ状態が続くので、細菌を増やすことになります。冷凍された食品の解凍は,冷蔵庫内で行うか、電子レンジを使いましょう。 作った料理は早めに食べましょう。 |
 |
  (中心まで加熱・調理器具の殺菌) 加熱して調理する食品は、中心部が75℃で1分以上、十分加熱しましょう。また、残った食品を温め直す時も十分に加熱しましょう。 調理器具は、漂白剤や熱湯などで定期的に消毒しましょう。 ただし、加熱できる食品は限られています。また、食中毒菌が作り出す毒素の中には熱に強いもの(黄色ブドウ球菌が作り出すエンテロトキシンなど)があるため、加熱したから大丈夫という過信は禁物です。 |
家庭での食事が原因の食中毒も多く発生しています。そこで、家庭でできる「食中毒の予防方法」をご紹介します。
家庭でできる6つのポイント
1 買い物をするとき
消費期限などをよく確認して購入し、温度管理が必要なものは早く持ち帰りましょう。
2 食品を保存するとき
冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下で保存し、詰めすぎないようにしましょう。
3 下準備のとき
生の肉・魚・卵を取り扱った後は、必ず手洗いをし、包丁・まな板・ふきんなどの台所用品は、使った後すぐに洗剤と流水でよく洗いましょう。
4 調理のとき
調理の前は必ず手洗いをして、食品を冷蔵庫から出したら早く調理し、加熱調理する場合は中心までしっかり火を通しましょう。
5 食事のとき
調理した食品は、室温で長く置かないで、早めに食べましょう。
6 食品が残ったとき
残った食品は、早く冷えるように容器に小分けをして冷蔵庫で保存しましょう。
食べるときは再加熱をし、怪しいなと思ったら思い切って捨てましょう。
詳しく知りたい方は…
○ 食中毒・食品監視関連情報(厚生労働省ホームページにリンク)
○ 家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(広島県ホームページにリンク)







