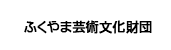研究紀要
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月8日更新
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第12号(2025年3月31日発行)
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第11号(2023年3月31日発行)
| 大前 勝信 | 野田正明とニューヨークのアーティストたち |
| 鈴木 一生 | 梅原龍三郎《仙酔島の朝》における独自様式の萌芽―国立公園洋画展覧会をめぐって |
| 筒井 彩 | 具体とその国際性―「フォンタナ カポグロッシ展」に見る交流関係 |
| 月村 紀乃 | ふくやま美術館所蔵の長尾美術館旧蔵刀剣について |
| 中村 麻里子 | 岡本豊彦と菅茶山 |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第10号(2021年3月10日発行)
| 大前 勝信 | 戦後の福山洋画壇と渡邉貞之 |
| 永井 明生 | 児玉希望《暮春》をめぐる一考察―風景画から花鳥画への移行について |
| 月村 紀乃 | 国宝《太刀 銘筑州住左(号江雪左文字)》の付属品について―失われた替鞘、替柄、由緒書― |
| 菊地 かの子 | ふくやま書道美術館の王冶梅 |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第9号(2019年3月26日発行)
| 大前 勝信 | 佐々田憲一郎と福山洋画壇について |
| 菊地 かの子 | 福田恵一の書簡にみる戦争の影―美術資料・島田薫荘氏宛書簡類の紹介を中心に― |
| 鈴木 一生 | 小林和作の風景画における構図―〈伯耆大山〉を中心として |
| 谷藤 史彦 | 藤井厚二論(2) |
| 吉川 咲子 | 【研究ノート】ジュゼッペ・パリッツィとフィリッポ・パリッツィの活動年譜について |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第8号(2017年2月28日発行)
| 安部 すみれ | 野田弘志資料研究―小説『湿原』挿画制作をめぐって― |
| 大前 勝信 | 野田正明:ラフカディオ・ハーンにまつわる造形表現の一考察 |
| 谷藤 史彦 | 藤井厚二論 |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第7号(2015年2月27日発行)
| 安部 すみれ | 【研究ノート】大村廣陽《古都神鹿》と制作資料について |
| 大前 勝信 | 安井曾太郎:様式美誕生における一考察 |
| 谷藤 史彦 | アドルフォ・ヴィルトとルチオ・フォンタナ―伝統性の問題をめぐって |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第6号(2012年12月1日発行)
| 高橋 哲也 | 中世における佐跡の評価について |
| 平泉 千枝 | 小林徳三郎の日記・書簡資料紹介―昭和17年から昭和22年までの画家のくらし― |
| 谷藤 史彦 | 評伝 高橋秀(2)―イタリアと日本の間で― |
| 谷藤 史彦 | 日本におけるルチオ・フォンタナの受容とその影響 |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第5号(2011年3月23日発行)
| 濱田 恒志 | 【研究ノート】大村廣陽作《光堂開扉》の制作意図 |
| 谷藤 史彦 | 評伝 高橋秀(1)―1950-60年代、国際化時代に画家として立つ― |
| 角井 博 | 日本における「張楷」の受容について |
| 高橋 哲也 | 藤原佐理筆書状《頭弁帖》について |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第4号(2007年7月24日発行)
| 平泉 千枝 | ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの自己形成期 |
| 大前 勝信 | 福山出身の洋画家、小泉成一について |
| 萬木 康博 | 藤井軍三郎旧蔵の黒田清輝自筆書簡について |
ふくやま美術館・ふくやま書道美術館 研究紀要 第3号(2005年7月21日発行)
| 谷藤 史彦 編 | 美術品調査:吉原英雄 版画作品目録 1995-2001 |
| 萬木 康博 | 横山大観の香川勝廣宛て書簡について |
ふくやま美術館 研究紀要 第2号(2003年3月30日発行)
| 石井 太 | 大村廣陽のスケッチ・素描・小下絵について |
| 大前 勝信 | 大村廣陽作《休み(習作)》について |
| 掛谷 美江 | 「大村廣陽文庫」について |
| 谷藤 史彦 | フォンタナの絵画空間について |
ふくやま美術館 研究紀要 創刊号(2001年3月13日発行)
| 石井 太 | 《麗子十六歳之像》と岸田劉生 |
| 大前 勝信 | 東郷青児《星座の女》にみられる表現の視点 |
| 掛谷 美江 | ふくやま美術館におけるレファレンス・サービスの実際 |
| 谷藤 史彦 | ジャコモ・バッラの「動き」の造形について |
| 宮内 ちづる | 絵本作家 佐野洋子の原点:『おじさんのかさ』における「執着からの開放」の考察 |
| 萬木 康博 | 《静物(赤き林檎二個とビンと茶碗と湯呑)》について―劉生静物画群のなかでの一考察― |
| 中野 政樹 | 彫金家清水南山の工芸観―作品批評の再検討― |