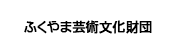略年表
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月30日更新
| 西暦 | 元号 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|---|
| 1748 | 延享 5 | 1 | 2月2日菅波樗平・半の長男として生まれる |
| 1766 | 明和 3 | 19 | 京都に遊学し市川某に古文辞学を学ぶが、後に那波魯堂に朱子学を、和田泰純に古医方を学ぶ |
| 1771 | 明和 8 | 24 | 西山拙斎が初めて茶山を訪ね、ともに三原へ観梅に行く |
| 1773 | 安永 2 | 26 | 初めて大坂の「青山社」に頼春水を訪ねる |
| 1775 | 安永 4 | 28 | 私塾を開く 藤井暮庵が入門する |
| 1780 | 安永 9 | 33 | 遊学中に大坂の「混沌社」社友と交わる |
| 1784 | 天明 4 | 37 | 門田氏宣と結婚する |
| 1786 | 天明 6 | 39 | 福山藩校弘道館教授に迎えられたが断る |
| 天明百姓一揆(~1787) | |||
| 1788 | 天明 8 | 41 | 藤井暮庵と広島・宮島に遊び頼杏坪・頼山陽と出会う |
| 『遊芸日記』が成る 『冬日影』が成る | |||
| 1792 | 寛政 4 | 45 | 福山藩儒医として五人扶持を給される |
| 塾経営に専念するため家業を弟恥庵(ちあん)に譲る | |||
| この頃、「黄葉夕陽村舎」・「閭塾」が現在の場所に開設される | |||
| 1794 | 寛政 6 | 47 | 『北上歴』の旅に出る 父樗平の『三月庵集』(やよいあんしゅう)を編集する |
| 1797 | 寛政 9 | 50 | 「黄葉夕陽村舎」が福山藩校の郷校となり、「廉塾」・「神辺学問所」と称する |
| 1800 | 寛政 12 | 53 | 弟恥庵が京都で病没する |
| 1801 | 享和 元 | 54 | 福山藩儒官となり藩校弘道館で講釈を始める |
| 1804 | 文化 元 | 57 | 福山藩阿部正精の命で江戸に赴く |
| 1805 | 文化 2 | 58 | 阿部正精に『福山志料』編纂を命じられる |
| 1807 | 文化 4 | 60 | 神辺大火で茶山宅は全焼、塾はまぬがれる |
| 1808 | 文化 5 | 61 | 門田朴斎が入門する |
| 1809 | 文化 6 | 62 | 頼山陽が廉塾の都講(塾頭)になる |
| 1810 | 文化 7 | 63 | 後に廉塾の後継者になる甥の子、菅三が生まれる |
| 1811 | 文化 8 | 64 | 頼山陽が廉塾を去る |
| 1812 | 文化 9 | 65 | 『黄葉夕陽村舎詩』前編が刊行される |
| 1813 | 文化 10 | 66 | 『三原梅見之記』が成る 北條霞亭が廉塾の都講になる |
| 1814 | 文化 11 | 67 | 阿部正精の命で江戸に赴く |
| 1818 | 文政 元 | 71 | 大和・吉野・京都に遊ぶ 『大和行日記』が成る |
| 1819 | 文政 2 | 72 | 『福山藩風俗問状答書』をまとめる |
| 1820 | 文政 3 | 73 | 門田朴斎を養子とする |
| 1823 | 文政 6 | 76 | 『黄葉夕陽村舎詩』後編が刊行される |
| 1826 | 文政 9 | 79 | 妻の宣が没する |
| 1827 | 文政 10 | 80 | 門田朴斎を離縁し、菅三を養子とする |
| 8月13日没する 川北村網付谷に葬られる | |||
| 1832 | 天保 3 | 『黄葉夕陽村舎詩』遺稿が刊行される |