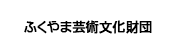漢詩の世界
田家 牡丹宿蝶 早到法城村 即事 元日口号 蛍七首 宿釣月楼 秋日雑咏(前半六首) 秋日雑咏(後半六首)
田家(でんか)
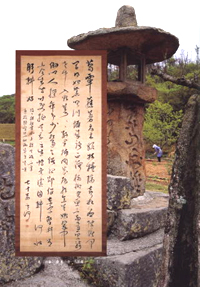 |
葛覃藤[ ]夏木瞑…葛覃(かったん)藤(とう)[まん]夏木(かぼく)瞑(くら)し 牧犢隔林聲相應…牧犢(ぼくとう)林(はやし)を隔(へだ)てて声(こえ)相応(あいおう)ず 陂塘閘開風始薫…陂塘(はとう)閘(こう)開(ひら)いて風(かぜ)始(はじ)めて薫(くん)じ 野川堰成路正濘…野川(やせん)堰(せき)成(な)って路(みち)正(まさ)に濘(ぬか)る 揚柳貫魚三両童…揚柳(ようりゅう)魚(さかな)を貫(つらぬ)く三両(さんりょう)童(どう) 累騎老牛入竹叢…老牛(ろうぎゅう)に累騎(るいき)して竹叢(ちくそう)に入(はい)る 竹叢数里擁閭巷…竹叢(ちくそう)数里(すうり)閭巷(りょこう)を擁(よう)し 屋影參差嫩翠中…屋影(おくえい)參(しん)差(し)たり嫩翠(どんすい)の中(なか) 僻郷人僕[ ]爭少…僻郷(へききょう)人僕(じんぼく)にして[かい]争(そう)少(すく)なく 相通乞假親隣保…乞假(きっか)相通(あいつう)じて隣保(りんぽ)親(した)しむ 東家鑿井常共汲…東家(とうか)井(せい)を鑿(うが)てば常(つね)に共(とも)に汲(く)み 北舎生兒時更抱…北舎(ほくしゃ)兒(こ)を生(う)めば時(とき)に更々(こもごも)抱(だ)く 嗟我平生懐憂虞…嗟(ああ)我(われ)平生(へいせい)憂虞(ゆうぐ)を懐(いだ)く 目耕何似躬耕好…目耕(もっこう)躬耕(きゅうこう)の好(よ)きに何似(いずれ)ぞ 隔下脱林字北上脱共汲二字 |
【大意】
田家の周りには葛や藤がはびこって昼なお暗い。放牧の牛の子が林を隔てて鳴きあっている。溜池の樋を抜く頃になると風が薫りはじめ、川に堰が降ろされると道はぬかるむ。二、三人の童が柳に魚を突き刺して提げ、老牛の背中に二人乗りして竹薮に隠れた。その竹薮は村里を抱き抱えるように長々と続き、家々は新緑の中にふぞろいに建っている。田舎の人は純朴で争い事は少なく、隣近所で物を融通し合って平和に暮らしている。東家に井戸を掘ると共に汲み、北舎に子どもが生まれるとかわるがわる抱いて皆で育てる。私は常々憂え悩んでいる。学問と農業、どちらがよいものか。
【作詩年代】1785(天明5)年 茶山38歳
【揮毫年代】1817(文化14)年 茶山70歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』前編2-16所収
牡丹宿蝶(ぼたんしゅくちょう)
 |
牡丹將欲歛 一蝶尚依依 恐被花包裹 通宵不得歸 茶山樵 牡丹(ぼたん) 将(まさ)に歛(かん)を欲(ほっ)し |
【大意】
牡丹の花は、まさにその盛りを過ぎ萎(しお)れようとしている。それなのに一匹の蝶は、牡丹に名残(なごり)を惜しむように飛んでいる。私が恐れるのは、牡丹の花が閉じて蝶をくるんで、夜通し家に帰れなくなってしまうことだ。
【作詩年代】1822(文政5)年 茶山75歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』遺稿2-2所収
早到法城村(つとにほうじょうむらにいたる)
 |
池氷知暖響鏗然 正是山陽[ ]後天 日出林頭風未動 清霜融作満郊烟 茶山樵 地氷(ちひょう)暖(だん)を知(し)って響(ひびき)鏗然(こうぜん)たり |
【大意】
池に張った氷が暖かさで音を立てて割れた。時候は十二月の山陽地方である。太陽が昇り、林の辺りにはまだ風が起こらず、真っ白な霜が解け出して野原一面に靄(もや)が漂ってきた。
【作詩年代】1816(文化13)年 茶山69歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』後編7-12所収
即事(そくじ)
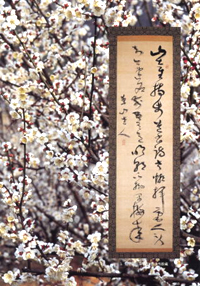 |
山童持帋道書詩 老嬾揮毫人所知 山童(さんどう) 帋(かみ)を持(も)って詩(し)を書(しょ)せと道(い)う |
【大意】
山の子どもが紙を持って来て詩を書けという。老いて揮毫するのは気の進まないことと皆も知っているとおり。今すみやかに求めに応じるには下心があってのこと。明朝早く梅の枝を折って来てほしいものだ。
【作詩年代】1827(文政10)年 茶山80歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』遺稿7-2所収
元日口号(がんじつこうごう)
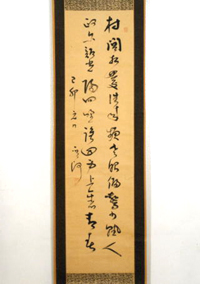 |
村閭相慶往來頻 老眼偏驚少熟人 村閭(そんりょ)相(あ)い慶(けい)して往来(おうらい)頻(しき)りなり |
【大意】
村里では、人々が祝いあって往来が盛んである。しかし、年をとった私にはなじみの人が少なくなったことに驚いている。政治もそうであるが、その輝かしい時も忘れられてしまう。誰が私の青春時代に思いをめぐらすだろうか。
- 口号・・・心に浮かぶままを吟じる詩
『黄葉夕陽村舎詩』では、識人としている部分を本書では塾人に、陽和を韶光にして書いている。
【作詩年代】1819(文政2)年 茶山72歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』後編8-13所収
蛍七首(ほたるしちしゅ)
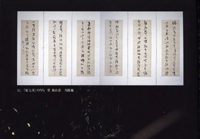
|
満渓蛍火乱昏黄 透竹穿藤各競光 満渓(まんけい)の蛍火(けいか) 昏黄(こんこう)に乱(みだ)る |
【大意】
谷川いっぱいの蛍が黄昏に乱舞している。竹の葉に透けとおり藤をくぐりぬけ各々光を競っている。詩を吟じながら歩いていて夜になっても心配はいらない。蛍の余った明かりを借りて谷川の橋を渡ればいいのだから。
|
雙影[][]出隊翔 愛看開闔近吾傍 双影(そうえい)[けいけい]として隊(たい)を出(い)でて翔(かけ)る |
【大意】
二匹の蛍が光ながら、仲間から離れて飛んでいく。光を点滅させながら、私の側に近寄ってくるのをいとおしく眺める。ふと、柳の繁みに隠れて姿が見えなくなったが、風が柳の糸を吹き束ねるとまた光を現した。
|
風收荷沼氣逾香 雲壓芽檐夜未凉 風(かぜ)は荷沼(かしょう)に収(おさ)まりて気(き)愈(いよいよ)香(かんば)し |
【大意】
風が蓮の生えた沼に吹き入ると、芳香がいよいよ芳しく、雲は芽の軒先におしかかり夜だというのにまだ涼しくない。蛍もまた明日の雨を知ってか、二、三匹が追いかけるようにして家の中に入ってきた。
|
連夜收來滿練嚢 柳陰懸照納凉場 連夜(れんや)収(おさ)め来(きた)って練嚢(れんのう)に満(み)つ |
【大意】
毎夜蛍を捕らえて練り絹の袋一杯にし、柳の木陰に懸けて納涼場を照らす。子どもは言う「蛍の火もまた本当の火だよ。団扇であおぐと燃えだしそうになり、手をかざせば暖かいよ」と。
|
檐聲纔斷夜朧朧 待霽群螢爭出叢 檐声(えんせい) 纔(わず)かに断(た)えて夜(よる)朧朧(ろうろう) |
【大意】
軒の雨の音がやっと絶えて、夜は薄明るい。晴れるのを待って、蛍の群れが争って草むらから飛び立つ。羽根は湿ってまだ屋根を越えて行くことができず、光がみどりの竹や青桐の繁みの中でためらっている。
『黄葉夕陽村舎詩』上欄には、武元君立(たけもと・くんりゅう)の「蛍を賦(ふ)して未だ許(この)如(ごと)き爛熟者(らんじゅくもの)を見ず」の詩評あり。
- 爛熟者…くわしく知る者
|
一星横迸度回塘 影落清波上下光 一星(いっせい) 横(よこ)に迸(はし)りて回塘(かいとう)を度(わた)る |
【大意】
一匹の蛍が、流れ星のように横に飛んで、池の堤をわたっていった。その姿は水に映って空中と水中とで光っている。飛んでだんだん低く下がって、誤って水に落ちたかと思うと、にわかに浮草の葉につかまってさらに高く舞い上がった。
『黄葉夕陽村舎詩』上欄には、頼山陽の「興(きょう)ずる蛍の伝神(でんしん)の最(さい)たるは、此(この)詩にあり」の詩評あり。
- 伝神…精神を伝える
屏風に書かれていない残りの一首は、つぎの詩である。
|
莊叟蝶夢狂空在 齊后蝉聲怨漫長 荘叟(そうそう)が蝶夢(ちょうむ) 狂(きょう)なること空(むな)しく在(あ)り |
【大意】
荘子が夢の中で蝶になったというのは狂気の沙汰であり、斉王の后が蝉となっていつまでも恨みがましく鳴いているというのも執念深すぎる。それに比べれば、蛍、お前は草の根が腐って後、変化したというが、それでいて美しい光を発するのは何と愛らしいではないか。
【作詩年代】1816(文化13)年 茶山69歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』後編7-3所収
宿釣月楼(ちょうげつろうにしゅくす)
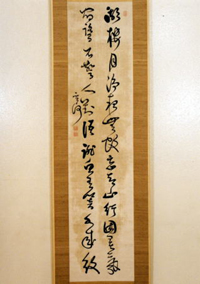 |
湖楼月淨夜無蚊 忘却山行困暑氛 湖楼(ころう)月(つき)淨(きよ)くして、夜(よる)蚊(か)無(な)く |
【大意】
湖のほとりの楼閣に月が清く、蚊のいない快適な夜となった。日中山あるきで苦しんだ暑さはどこかに消え、宿る鷺も人の話し声ぐらいでは驚かず、魚が飛び上がって音を立てると、波紋が広がっていく。
※後藤蘆洲・濱本鶴濱共編による「黄葉夕陽村舎詩人名地名考」によると、釣月楼は、玉島のササ屋多源治の楼名とある。『黄葉夕陽村舎詩』上欄には北條霞亭(ほうじょうかてい)の詩評があり、「三、四老杜の絶句に似たり」と杜甫の絶句に似ていると書いている。
【作詩年代】1809(文化6)年 茶山62歳以前
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』後編2-16所収
「秋日雑咏」(しゅうじつざつえい) 前半六首
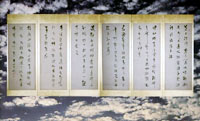
|
蓮已摧殘菊未開 此時秋物各爭才 蓮(はす)已(すで)に摧残(さいざん)し菊(きく)未(いま)だ開(ひら)かず |
【大意】
蓮の花は既に散り、菊の花はまだ開かない。この季節は、秋の草花が各々その美しさを競う。女郎花(おみなえし)は人を遮っては、金色の粟粒を積み上げ、たびらこは道端に玉杯を捧げる。
|
鳳僊頗美冶容多 鶏髻雖妍色帯奢 鳳僊(ほうせん)は頗(すこぶる)る美(び)なれども冶容(やよう)多(おお)く |
【大意】
鳳仙花(ほうせんか)はいかにも美しいが、その姿にはなまめかしいところがあり、鶏頭(けいとう)もまた美しいが、その色は奢(おご)りを帯びている。どちらが美しいか、私は蝶に尋ねてみようと思う。私が最も愛する花はどちらなのかを。
|
我圃牽牛種頗奇 傳言本自[]州移 我(わ)が圃(ほ)の牽牛種(けんぎゅうしゅ)は頗(すこぶ)る奇(き)なり |
【大意】
わが畑の朝顔の種類は相当に変わっている。言い伝えによると、もと中国のしょう州から移したものとのことだ。色は濃く花は大きくて長い間咲き続け、曇りの日はいつも夕方になってもまだ萎まずにいる。
|
[][]秋卉媚煙霏 風意[][]小釣磯 [いずい]たる秋卉(しゅうき) 煙霏(えんぴ)に媚(こ)び |
【大意】
咲き誇る秋の草花は靄(もや)に媚び、魚釣の磯では風の気配が清らかである。夕日が沈もうとして照らし出すと、一つがいの黄色い蝶が草むらを出て飛び立つ。
|
午暖叢間尚露華 殘黄耄紫相交加 午(ひる)暖(あたた)かにして 叢間(そうかん)尚(な)お露華(ろか)あり |
【大意】
暖かい昼間だというのに、草むらの間にはまだ露の玉があり、散り残った黄色の花や枯れた紫色の花が入り混じっている。カマキリは人がやって来るのをじっと見て、静かに芦の花から蓼(たで)の花に移っていった。
|
矮松疎篠兩三家 芋圃[]畦路幾叉 矮松(わいしょう) 疎篠(そじょう) 両三家(りょうさんか) |
【大意】
小さな松と、まばらな篠竹が生えた山里に二、三軒の家がある。芋畑と蕎麦畑の中の道は、幾筋にも分れている。子どもたちが帰ってきて、自慢顔をしている。 見ると数本の茸を、ちがやに突き通している。
「秋日雑咏」(しゅうじつざつえい) 後半六首
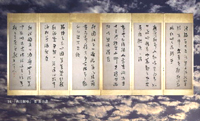
|
洛陽花子已能生 寸許新芽緑欲平 洛陽(らくよう)花子(かし) 已(すで)に能(よ)く生(しょう)ず |
【大意】
なでしこの種子がすでに芽をだし、一寸ばかりの新芽が緑のじゅうたんを作ろうとしている。さらに喜ばしいのは、古い根がいまだに枯れずにいて、たまに紅の遅咲きの花を咲かせることだ。
|
梧竹秋聲入晩晴 遥看遠水日添明 梧竹(ごちく) 秋声(しゅうせい) 晩晴(ばんせい)に入(い)る |
【大意】
桐と竹が秋風に吹かれ枯れ葉を落とし、夕方になって雨が上がり晴れる。遥かを見れば遠くの川が日ごとにはっきりと見え出してきた。軒端に生える萩を風がゆすると、露は窓の格子に落ちて点々として清らかである。
|
黄雲百頃擁人家 暮[]凉生十里沙 黄雲(こううん) 百頃(ひゃくけい) 人家(じんか)を擁(よう)す |
【大意】
一面の田に稲が実り、黄色い雲に包まれたように人家を抱きかかえ、夕暮れの谷間に涼気が生じて長く砂の川がつづいている。山里にはもう雪が降ったのかと疑いつつ見ると、村中が秋日和に橦の花を乾かしているのだ。
|
村園秋色日凄清 籬下陰蟲書亦聲 村園(そんえん) 秋色(しゅうそく) 日々(ひび)に凄清(せいせい) |
【大意】
村里の秋景色は日に日に清く澄みわたり、まがきの下では秋の虫が昼間でも鳴いている。橦のわたばなは競って開き、枝はいよいよ重くなり、ひょうたんは熟れだし、たながまず傾く。
|
隣僧乞我小園芳 蕃菊胡枝秋海棠 隣僧(りんそう) 我(われ)に小園(しょうえん)の芳(はな)を乞(こ)う |
【大意】
隣の僧が、私に庭の花を求めてきた。蕃菊と萩と秋海棠を差し上げる。まもなくすると竹籠を携えてお返しに来た。見ると泥がついたままの松茸で、台所一面にそのよい香りを放っている。
|
秋深園卉日凋衰 也喜清芳無歇時 秋(あき)深(ふか)く園卉(えんき)は日々(ひび)に凋衰(ちょうすい)す |
【大意】
秋が深まり庭の草花は日々しぼみ衰えていくが、また清らかな香りが途絶えるときがないことを喜ぶ。日かげのこの静かな場所に誰が小春のたよりを伝えたものか。山茶花(さざんか)がすでに菊の花に先んじて花を開いている。
【作詩年代】1816(文化13)年 茶山69歳
【出典】
『黄葉夕陽村舎詩』後編7-9所収