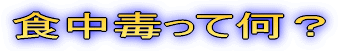本文
食中毒とは?
▼食中毒とは、食中毒の原因となる細菌やウイルスが付着した食品や、有毒・有害な物質が含まれた食品を食べることによって、腹痛・下痢などの健康被害が起こることです。
また、人から人へ直接感染するコレラや赤痢などの感染症であっても、食品を介して腹痛・下痢などが発生すれば食中毒として扱われます。
なお、栄養障害などは、食中毒に含まれません。
▼食中毒菌やウイルスが食品に付着しても、腐敗と異なり、「味」「色」「におい」が変わることはありません。
▼主な症状は、胃腸炎(下痢、腹痛、嘔吐など)ですが、発熱、倦怠感など、風邪のような症状の時もあります。
▼通常、人から人に直接うつることはありませんが、腸管出血性大腸菌O157、赤痢菌、ノロウイルスなどは感染力が強いため、人から人へ感染することがあります。
もし、腹痛や下痢、発熱など体に異常があるときは、医師の診察を受けましょう。
食中毒の分類や予防法など
○食中毒予防の基本は手洗いです [PDFファイル/625KB]
○定期期的な検便で食中毒を予防しましょう [PDFファイル/288KB]
○ノロウイルス対応マニュアル(家庭編・施設編),家庭でできる消毒液の作り方
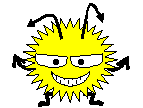
食中毒の分類
食中毒は,一般的に次のように分類されます。
| 食 中 毒 |
微生物 によるもの |
細菌性 | 感染型 | サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、エルシニアなど |
| 毒素型 | 黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌など | |||
| その他 | ウェルシュ菌、病原大腸菌(腸管出血性大腸菌O(オー)157など)など | |||
| その他の細菌性 | 赤痢菌、コレラ菌、リステリアなど | |||
| ウイルス性 | ノロウイルス(旧名称:小型球形ウイルス)など | |||
| 原虫類性 | クリプトスポリジウム、サイクロスポラなど | |||
| 自然毒 によるもの |
植物性 | じゃがいもの芽、毒キノコ、トリカブトなど | ||
| 動物性 | フグ毒、貝毒、毒カマスなど | |||
| 化学物質 によるもの |
誤用・不適正混入 | 農薬、殺そ剤、洗浄剤など | ||
| 環境汚染物質 | 有機水銀、カドミウム、ヒ素、鉛など | |||
| アレルギー様のもの | ヒスタミンなど | |||
| 寄生虫 によるもの |
生鮮魚介類や獣生肉などから感染 | アニサキス、顎口虫、トキソプラズマなど | ||
食中毒の特徴と予防法
細菌性 (・・・生育条件が整えば,食品中で大量に増殖)
サルモネラ属菌 |
|
特 徴 |
牛・豚・鶏などの動物の腸管や、河川・下水など自然界に広く分布しています。サルモネラには約2500種類以上の血清型があるといわれ、その中でもサルモネラ・エンテリティディスによるものが多いといわれています。 サルモネラ・エンテリティディスは、家畜の腸管内に生息しているので食肉が原因となるほか、鶏卵及び鶏卵加工品が疑われる食中毒も多く発生しています。 |
| 原因食品 | 主に、牛・豚・鶏などの食肉や卵などの畜産食品、ウナギ、スッポンなど。 二次的に汚染された食品。 |
| 主な症状 | 急な発熱(38~40℃)、吐き気、嘔吐、腹痛、激しい下痢などの胃腸炎症状。 通常は4~5日で回復に向かいますが、症状が進むと有熱期間が2週間近く続くことがあります。 |
| 潜伏時間 | 6~72時間(通常12~24時間) |
| 予防方法 | 食肉・卵などを扱った器具・容器・手指は、そのつど洗浄消毒してください。 食肉や卵の調理の際は、食品の中心部まで十分に加熱(75℃1分以上)してください。 ひび割れた卵や破卵の使用を避け、また卵の割置きはやめてください(生食用の賞味期限に注意)。 ネズミ・ゴキブリ等の衛生害虫を駆除してください。 ペットを調理場内に入れないでください。 |
腸炎ビブリオ |
|
特 徴 |
塩分を好み、原因となる食品は海産魚介類がほとんどです。海水温の上がる6月上旬から9月初旬にかけて海水中で大量に増殖するため、夏季の海産魚介類の扱いには特に注意が必要です。 |
| 原因食品 | 主に、生鮮魚介類およびその加工品。 |
| 主な症状 | 激しい腹痛(特に上腹部)・下痢・発熱(37~40℃)・嘔吐などの急性胃腸炎症状。 通常は2~3日で回復しますが、症状が進むと水様性の下痢を1日に10回以上起こすこともあります。 |
| 潜伏時間 | 4~28時間(通常10~18時間) |
| 予防方法 | 腸炎ビブリオは、真水・熱に弱いため、魚介類を生で食べる時は特に流水(真水)でよく洗い、加熱して食べる時は中心部まで十分に加熱してください。 魚介類の調理器具は一般用とは区別し、使用後は十分に洗浄・消毒して二次汚染を防いでください。 刺身など生で食べるものは、冷蔵保存(4℃以下)を徹底し、できるだけ早く食べきってください。 |
カンピロバクター |
|
特 徴 |
牛・豚・鶏などの家畜や犬・猫などのペットの腸管内に存在しており、特に鶏の保菌率が高いといわれています。 これらの動物の糞に汚染された肉や水を介して感染が起こります。 少量の菌量でも発症し、発症までの潜伏期間が長いという特徴があります。 乾燥や熱に弱いですが、10℃以下の低温では長時間生存します。 微好気(少量の酸素がある状態)という特殊な条件で増殖します。 |
| 原因食品 | 鶏肉などの生食または、加熱不十分が原因になります。 家畜等の糞尿に汚染された水が原因となることもあります。 |
| 主な症状 | 発熱(38~39℃)・倦怠感・腹痛・下痢など。 |
| 潜伏時間 | 2~7日(通常35時間) |
| 予防方法 | 生肉などは、早めに調理し、十分加熱してください。 生肉と調理済食品は別々に保管してください。 手洗いや調理器具の洗浄・消毒を十分に行ってください。 |
| 参 考 | → Q&A(厚生労働省HPにリンク) |
黄色ブドウ球菌 |
|
特 徴 |
顕微鏡で見ると、ブドウの房のように集まっていることから名付けられました。 ヒトの生活環境に広く分布し、健康な人でも喉や鼻の中、毛髪などからでも検出されます。 この菌は増殖する時にエンテロトキシンという毒素をつくり、この毒素を食品と一緒に食べることによって食中毒がおきます。 菌は熱に弱いですが、毒素は100℃30分の加熱でも分解されません。 |
| 原因食品 | おにぎり、仕出し弁当、生菓子など。 |
| 主な症状 | 特に吐き気・嘔吐(激しい)、腹痛・下痢。 |
| 潜伏時間 | 1~6時間(通常3時間) |
| 予防方法 | 手指などに切り傷や化膿性疾患のある人は、食品に直接触れることや調理をさけてください。 (やむを得ない場合はビニル手袋をしてください。) 調理の際に帽子やマスクの着用してください。 食品は10℃以下で保存し、菌の増殖を防いでください。 弁当やおにぎりは冷ましてから包装してください。 |
ウェルシュ菌 |
|
特 徴 |
ヒトや動物の糞便や土壌、下水などの自然環境に広く分布しています。 耐熱性の細菌であり、「加熱済みの食品は絶対安心」という誤った認識が食中毒を引き起こす一因となっています。 一度に大量調理された食品が原因となりやすく、給食を原因とする大規模集団発生を引き起こすことがあります。 空気のないところで発育する嫌気性細菌です。 |
| 原因食品 | 同一容器で大量に加熱調理され、長時間室温に放置されたカレーライス・シチュー・めんつゆなど。 |
| 主な症状 | 下痢・腹痛。症状は比較的軽症で1日くらいで回復します。 |
| 潜伏時間 | 6~18時間(通常12時間) |
| 予防方法 | 前日調理を避け、加熱調理したものはなるべく早く食べてください。 調理後、食べるまで時間がかかる場合は、冷却後、冷蔵保存してください。 食べる前に再加熱を十分行ってください。 |
腸管出血性大腸菌 |
|
特 徴 |
大腸菌のうち、ヒトに病原性を有するものを病原大腸菌といいます。このうちヒトの腸管内で毒性の強いベロ毒素を産生して出血性の下痢を引き起こすものを腸管出血性大腸菌といい、血清型によりO1・O26・O157・O111などが知られています。 O157は牛など家畜の腸管に存在し、糞便が様々な経路で食品や水を汚染して感染するとされます。 菌は熱に弱く、75℃1分の加熱で死滅します。 少量の菌でも発症し、感染力も強いです。患者の便などを介して人から人への二次感染も起こるので注意が必要です。 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で「3類感染症」に指定されています。 |
| 原因食品 | 家畜などの糞尿に汚染された水・食肉・生野菜など。 |
| 主な症状 | 水様性の下痢に始まり、血便と腹痛などの出血性大腸炎を引き起こします。 重症の場合、溶血性尿毒症症候群を起こし、死に至ることもあります。 |
| 潜伏時間 | 4~9日 |
| 予防方法 | 食べる前に食品の中心部まで十分加熱(75℃1分以上)してください。 まな板・包丁・ふきんなど調理器具は十分洗浄し、熱湯などで消毒してください。 井戸水等、水道以外の水を使用する場合は必ず消毒してください。 手洗いを十分に行ってください。 |
| 参 考 | → Q&A(厚生労働省HPにリンク) |
ウイルス性 (・・・特定の生物の細胞内でのみ増殖)
ノロウイルス ←SRSV(小型球形ウイルス)は「ノロウイルス」と名称が変わりました |
|
特 徴 |
冬季を中心に、年間を通して胃腸炎を起こします。 ヒトの体内(主に小腸)でのみ増殖します(食品中では増殖しません)。 感染経路は経口感染(口から体内に入ること)です。 感染者のおう吐物やふん便等から二次感染を起こすことがあります。 学校や保育所などの集団給食施設での発生もみられますが、原因食品が特定できない事例が多いです。 |
| 原因食品 | 二枚貝(特に生カキ)・ケーキ・サンドウィッチ・サラダなど、多様な食品。 |
| 主な症状 | 下痢(激しい水様便)・嘔吐・腹痛・発熱(38℃以下)。 通常は3日以内で回復します。 |
| 潜伏時間 | 24~48時間 |
| 予防方法 |
食材の中心部までしっかり加熱(85℃~90℃で90秒以上)してください。 |
| 参 考 | → Q&A(厚生労働省HPにリンク) → ノロウイルスによる食中毒に気をつけましょう |
その他(自然毒等)
ジャガイモの芽(ソラニン類) |
|
特 徴 |
ソラニン類はジャガイモの芽や皮(特に緑色になった部分)に多量に含まれます。 未成熟のジャガイモにも多量に含まれます。 学校菜園や家庭菜園で栽培したジャガイモよる中毒例がほとんどです。 |
| 主な症状 | 腹痛、おう吐、下痢、めまいなど。意識障害を起こすこともあります。 |
| 潜伏時間 | 食後20分~数時間 |
| 予防方法 | 芽は深く取り除き、皮は厚めにむいて調理をしてください。 特に皮が緑色になった部分は、しっかり取り除いてください。 未成熟の小型のジャガイモは食べないでください。 ジャガイモは冷暗所に保管し、日光に当てないでください。 |
毒キノコ |
|
特 徴 |
植物性自然毒による食中毒のほとんどが、毒キノコによるとされています。 採取したキノコを、自己流で鑑定して食べた結果発症するケースが多いです。 外見だけでは毒性を判断できません。 キノコ全体について、未知の部分が多く、毒性についても未解明な点が多いです。 |
| 主な症状 | 胃腸毒:おう吐、腹痛等。 神経毒:発汗、幻覚、麻痺等。 重症の場合は死に至ることもあります。 |
| 潜伏時間 | 食後10分~6時間以上 |
| 予防方法 | 野生のキノコの鑑定は、専門家に依頼してください。 知らないキノコは「採らない」「食べない」「人にあげない」 ※食用であっても、キノコは生食を避け、食べ過ぎないでください。 |
フグ毒(テトロドトキシン) |
|
特 徴 |
毒力は青酸カリの1000倍に匹敵するとされます。 フグの種類・部位・季節によって毒力が異なり、一般に産卵期(12月~6月)が最も毒性が強いとされます。 熱に対して極めて強いです(4時間の煮沸でも分解されません)。 |
| 主な症状 | 発症は早く、口唇や舌の痺(しび)れに始まり、頭痛・吐き気・歩行困難・言語障害・呼吸困難などを引き起こし、重症の場合は死に至ります。 中毒に気づいたら、胃腸内の毒成分を一刻も早く嘔吐排泄させるなどの応急処置が必要です。 |
| 潜伏時間 | 食後20分~1時間 |
| 予防方法 | フグの素人料理はしないでください。 ※福山市ではフグの処理・販売などについて「福山市ふぐの処理等に関する条例」を定めて指導しています。 |
| 参 考 | → フグによる食中毒に気をつけましょう! |
貝毒 |
|
特 徴 |
海水中の有毒プランクトンを捕食して蓄積した二枚貝を食べることにより発症します。 この貝毒の原因となるプランクトンは、一般に、海水温度が14℃前後となる4月中旬から下旬にかけて出現数がピークとなります。 |
| 原因食品 | ホタテ貝・ハマグリ・アサリ・カキなどの二枚貝。 |
| 主な症状 | 麻痺性貝毒:食後30分程度で手足の痺れ、めまい、眠気など。重症の場合は呼吸麻痺で死に至ることもあります。 下痢性貝毒:食後1~2時間で下痢・嘔吐・腹痛など。 |
| 予防方法 | 広島県では貝毒の検査体制を実施しており、規制値を超えた場合販売等を禁止して、毒化した貝類が市場に出ないようにしています。 ※貝毒が発生した場合は、直ちに県から新聞・TVなどを通じて広報を行います。 貝毒発生時には、発生地域において該当する二枚貝類を自分で採取したり食べたりしないようお願いします。 |
ヒスタミン |
|
| 特 徴 | ヒスタミンが含まれる食品を食べることによってアレルギーのような症状を起こします。 一定量を超えるヒスタミンが体内に入ることにより発症します。 |
| 原因食品 | 鮮度の落ちたサンマ、サバ、イワシなどの赤身の魚。 サバの煮付け、味付け缶詰めなど。 |
| 主な症状 | 顔面紅潮、じんましん、頭痛、発熱など。6~10時間で回復します。 |
| 潜伏時間 | 食後5分~1時間 |
| 予防方法 | できるだけ新鮮なものを食べてください。 |
アニサキス(幼虫) |
|
特 徴 |
クジラ、イルカなどの海産ほ乳動物を宿主とする回虫(寄生虫)の一種です。 中間宿主であるイカ、アジ、サバなどを生食とすることによって幼虫に感染します。 ヒトの胃壁や腸壁に幼虫(大きさ約2~3cm)が食い込み、激しい腹痛が起きます。 ヒトは宿主にならないので、最終的に体外に排泄されるといわれています。 ※アニサキスによるアレルギー反応が起こる場合もあります。 |
| 原因食品 | アジ、サバなどの海産魚やイカ類の生食(刺身、寿司など)。 |
| 主な症状 | 激しい腹痛、おう吐などの胃腸炎症状。 じんましんなどのアレルギー症状を起こすこともあります。 |
| 潜伏時間 | 食後数時間 |
| 予防方法 |
海産魚やイカ類の生食に注意してください(十分な加熱または冷凍により死滅します)。 |
※潜伏時間=感染してから発症するまでの時間