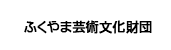2025年度 年間スケジュール
ふくやま書道美術館 2025年度展覧会予定
※内容や日程等、変更する場合があります。
所蔵品展
【観覧料】一般150円(120円)、高校生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金
【会場】ふくやま書道美術館 常設展示室・展示室
・春の所蔵品展「一行書の魅力」
【会期】2025年4月4日(金曜日)~5月6日(火曜日・休日)
一行書は縦長の紙に、禅語や漢詩の中から抜いた五言や七言等の佳句を揮毫したものです。短く簡潔な内容で理解しやすく、一字一字を大書でき、ダイナミックに表現ができる点で好まれています。一行書の魅力に触れてみてください。
・夏の所蔵品展1「対聯の魅力」
【会期】2025年5月10日(土曜日)~6月14日(土曜日)
対聯は、同じ形式で意義の対応する二句を並べて用いた「対句」を、門柱や家屋の入口の壁に書いたり、布や紙に書いて軸にしたものです。中国の生活文化における伝統的な習慣から生まれた対聯の書の魅力を感じてください。
・夏の所蔵品展2「一緒に見る 家族の書」
【会期】2025年7月4日(金曜日)~8月24日(日曜日)
作品を制作した各作家の略歴に着目した時、他の作家と家族・親族の関係をもつ作家が多いことが分かります。本展では「家族」をテーマに、時代をつなぐように書文化を築き上げてきたそれぞれの家族の書をご紹介します。
・秋の所蔵品展1「没後20年 中室水穂」
【会期】2025年8月29日(金曜日)~10月19日(日曜日)
没後20年を迎える福山市出身のかな書家・中室水穂(1935~2005)は、桑田笹舟・三舟父子に師事して書の道を進みました。古筆や料紙の研究により培われた表現だけでなく、墨跡調の力強い漢字表現にも取り組んだ中室水穂の創作の軌跡を辿ります。
・秋の所蔵品展2「文房具を愛でる」
【会期】2025年10月24日(金曜日)~12月14日(日曜日)
文房とは、もともと文書を司る地位を意味し、後に書画を鑑賞する書斎、そして宋代には文房具を意味するようになりました。本展では、文房四宝と呼ばれる筆・墨・硯・紙のほか、印材や筆筒、水滴などを展観し、文房具の優雅な趣をご堪能いただきます。
・冬の所蔵品展1「気になる!?怪物たちの書と絵画」
【会期】2025年12月20日(土曜日)~2026年2月8日(日曜日)
書風において独特奇怪なことから「揚州八怪」と称された書家たちがいます。この八人の怪物として名を連ね、中国・清代の康熙末頃から乾隆期にかけ活躍した、高鳳翰、鄭板橋、金農、李鱓の書画を中心に紹介します。
・冬の所蔵品展2「金石を見つめる ―碑学派の人たち」
【会期】2026年2月13日(金曜日)~2026年3月29日(日曜日)
清代の嘉慶期から清末に至るおよそ100年の間は、碑学派と呼ばれる書人が活躍した時代です。それまで書法は法帖を中心として学ばれていたのに対し、漢・魏、北朝におよぶ石刻や、篆書や金文など古代の文字に着目する動きが盛んになりました。金石を探究した人々の、多様な書表現をお楽しみください。
普及事業
【観覧料】無料
【会場】ふくやま美術館 2階 多目的室
・第20回 一緒にかく古代文字展
【会期】2025年8月1日(金曜日)~8月17日(日曜日)
漢字の基となった古代文字を家族や友だちと一緒にかくワークショップを行い、その作品を表装して展示します。のびのびとした楽しい作品が並びます。
・ETOをかく2026新春展
【会期】2026年1月2日(金曜日)~1月18日(日曜日)
2026年の干支「午」の絵や文字を筆で書いた作品を募り、届けられたすべての作品を展示します。新春に相応しい赤い台紙に、作品がずらりと並んだ展示風景は見応えあります。
・第21回 ふくやま書道美術館臨書展
【会期】2026年1月27日(火曜日)~2月15日(日曜日)
書を学ぶ人が通る道「臨書(昔の優れた筆跡(古典)を手本に見て書くこと)」。当展覧会では、学生たちが臨書した作品を「所蔵品臨書の部」と「自由臨書の部」で募り、選ばれた作品を表装して展示します。
上記の展覧会予定が載っている年間カレンダー(三つ折り/PDF画像)はこちらをクリック! [PDFファイル/3.18MB]